学部紹介 微生物とビッグデータ処理
バイオインフォマティックス技術者認定試験 合格
- 名前
- 奥田 重将 さん
- 所属
- 生命科学部3年(取材当時)
- 出身
- 秋田県立秋田高等学校
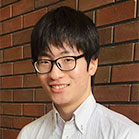
私の実家は酒蔵であり昔から糀カビ・酵母菌などの微生物に親しんできました。そのため、微生物を研究したいという強い想いがありました。微生物には従来の方法では解明しきれないほどの多様性があり、新たに研究を進めるためには膨大なデータを処理する能力が必要となります。そこで私は生命科学と情報学が融合したバイオインフォマティクス技術者試験を受験しました。
資源生物学及びバイオ情報科学の講義において“隠れマルコフモデル”(塩基配列ATCGの確率分布の変化を示したモデル)や“距離行列法”(DNA配列の違いの差から進化的な近さを図示する方法)など、今まで知らなかった概念を学び、自分の世界が広がるような感覚がありました。そして先生からの勧めもあり資格取得を決意しました。
勉強方法としては、まず公式HPに掲載してあるキーワード集を片端から調べ上げて分野別にノートにまとめ、必要に応じて図を付加しました。生物系に関しては今までの講義で学習したことが多く出てきますが、情報系は未知であったので重点的に調べました。ここで、バイオ情報科学の講義で教わった2進数・16進数の計算や分子系統解析は復習し、それでも網羅しきれない部分は専門用語が網羅的に掲載されている『バイオインフォマティクス辞典』や、講義形式で多様な図とともに必要要素が明快に掲載している『東京大学 バイオインフォマティクス集中講義』などの参考書を使用し理解しました。
そしてHPにある過去問を解き、誤答した問題は印をつけ、またノートを見返すことで復習し覚えきれていない箇所を補完していきました。同じ問題は3回ほど解き、複数回誤答したものやどうしても不安であるものはノートのその箇所に印をつけて本番直前まで見返しました。
いざ試験を終えると書物やニュースなどで書かれてあるものを自然とバイオインフォマティクスの視点から見る習慣がついていることに気づき、実生活に知識の繋がりが多くなりました。今後は就職活動や仕事において活かして行きたいです。
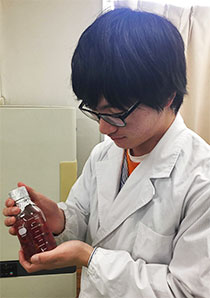
参考書
-
バイオインフォマティックス辞典
-
東京大学 バイオインフォマティックス集中講義








