ニュース&トピックス 分子生命科学科 教員インタビュー第3回 藤川 雄太 先生
- 生命科学部
- その他
- 分子生命科学科
2020.04.01
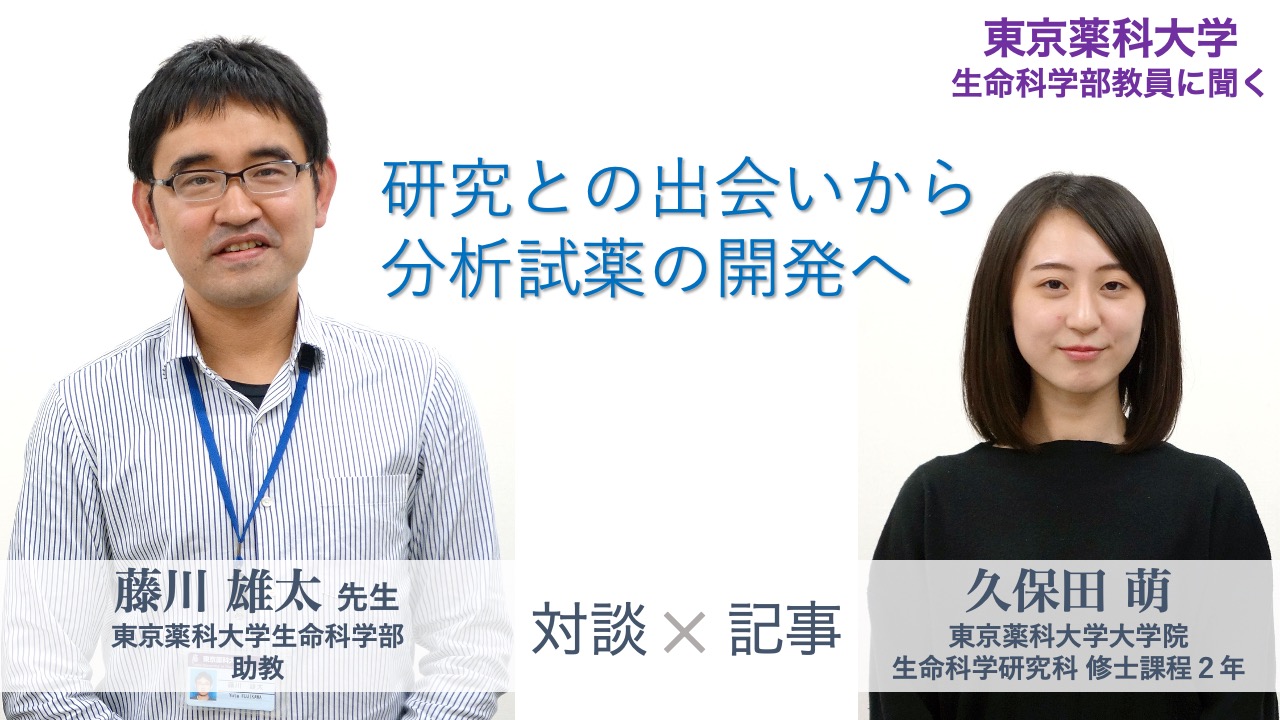
分子生命科学科 教員インタビュー第3回 藤川 雄太 先生
インタビュワー 久保田 萌 (生命分析化学研究室 修士2年)
久保田:本日はお話をする機会をいただきまして、ありがとうございます
今日は、先生の研究との出会いや研究内容についてお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします
藤川:はい、なんだか緊張しますね(笑)
こちらこそ、よろしくお願いします
 研究との出会い
研究との出会い
久保田:早速ですが、先生が研究と出会ったきっかけを教えてください
藤川:大学入試前に読んだ免疫学の本が面白くて、その著者が千葉大の先生だったのと、生物から物理まで色々学びたかった(あと薬剤師の資格も取っておきたかった…)ので、薬学部に入学しました
大学で学ぶうちに、免疫以外にも視野が広がってきまして、興味の方向も少しずつ変化してきました
研究には様々な手法を駆使して新しいことを発見する研究と新しい研究手法や道具(ツール)を作るという研究がありますが、後者の研究ツールの開発に強く惹かれるようになったんです
例えばドラえもんの道具を使うのではなく、作る方に興味が湧いたことになります
久保田:視野が広がるって大学で学ぶ醍醐味ですよね
藤川:それで、大学院進学先もそのようなツール開発ができるところを探していました
たくさん回った研究室のうち、後に僕の指導教員になる東京大学の先生と出会いました当時3年生の僕の勉強不足で研究内容はちんぷんかんぷんでしたが、説明してくださる先生の熱意と人柄が垣間見え、この先生の元で研究したい!と思いました
実は友達に教えてもらって知った研究室であり、偶然の出会いでしたが、ご縁だと思ってその先生の研究室に入って、 そこで今の仕事に通じる研究を開始しました
久保田:偶然の出会いにご縁を感じるなんて素敵ですね
 ドイツでの研究
ドイツでの研究
久保田:東京薬科大学に赴任する前はどちらで研究していたんですか?
藤川:ドイツの大学で、組織の中で酸化ストレスをどうやって測るかという研究していました
実は、留学先の教授にはじめに留学を申し込んだ時に英語でのコミュニケーション能力不足という理由で一度断られたんですよ(笑)
久保田:えっ!それでどうしたんですか?
藤川:その時にもらったEメールがとても丁寧で、その時には実績もほとんどなかった僕に、今後どうするべきか等々のアドバイスがびっしりだったんです
それで、これはこの教授のところに留学すれば研究以外の社会勉強もできるだろうと思って、「それでもやっぱり学ばせてほしい」という固い意思を伝えて、なんとか受け入れてもらえることになりました
僕は昔からそういうところがあって、身体が先に動いちゃうんです
久保田:すごいガッツですね!
でも、よくわかります、私もそういうところありますから(笑)
 分析試薬の開発研究について
分析試薬の開発研究について
久保田:さて、先生の開発された分析試薬GSTP1 Greenが、先日商品化されたと話題になりました [ 記事はこちら ]
どのようなことができる試薬なんですか?
藤川:私たちの研究グループが開発したものは、Pi-class Glutathione S-Transferase (GSTP1)と呼ばれる酵素の活性を生きた細胞で観察できるGSTP1 Greenという蛍光試薬です
この試薬は、似たような分子がたくさんあるGSTという酵素のうち、がんでたくさん存在するGSTP1という分子に特異的で、反応によって緑色蛍光を発するようになるんです
久保田:さまざまな酵素がある中で、GSTP1に注目したのはなぜですか?
藤川:GSTP1は細胞のがん化や抗がん剤耐性に関わることが知られる酵素です
このような酵素の活性を簡便に観察できれば、GSTP1ががんでどんな働きを担っているのかを調べることができるようになる、あるいはがんの検出プローブとして使えるかもしれないと考えました
しかし、研究を始めた2009年当時、GSTP1を検出する蛍光プローブはありませんでした
そもそも、がん研究に利用できる蛍光プローブ試薬も数えるほどしか存在しませんでした
久保田:細胞のがん化プロセスや薬剤耐性を研究するのにGSTP1活性を観察できる蛍光プローブ試薬を活用できるのですね
試薬の開発で苦労したところはどこですか?
藤川:試薬の開発では、対象分子以外と反応しない性質(特異性)や、対象分子の数が少なくても検出できる性質(感度)の向上を目指します
様々な化合物を設計して試すのですが、色々なアイデアを試しても上手くいかず、時間ばかりが過ぎていくという壁にぶつかった時ですね
久保田:どのようにその壁を乗り越えたんですか?
藤川:ブレークスルーは、一緒に研究していた博士課程の森君のアイデアだったんですよ
そのとき、僕は程々の性能の化合物で妥協しようと考えていたところだったんですけど、森君は納得できるものができるまで諦めなかったんです
僕が提案したアイデアだけではなく、それを更に一歩広げて設計した化合物を試してくれたんです
そうしたら、それが大当たりしました(笑)
そのおかげで、特許取得や商品化につながりました
久保田:開発された蛍光プローブは今後どのように活用されていきますか?
藤川:これまでお話ししたように、GSTP1という酵素の機能を調べることだったり、阻害剤を探す研究だったりで新しい発見があると、試薬の開発者としては嬉しいです
おそらくそれ以外にも活用できる場面があると思いますが、正直に言うと僕らだけではアイデア不足です
専門家の皆さんはもちろんのこと、先入観のない学生さんのアイデアなども積極的にとりいれながら用途を拡大していきたいと考えています
久保田:なるほど、学生のアイデアでも研究に貢献できることがあるってことですね!!
 アイザック・ニュートン
アイザック・ニュートン
藤川:ところで、万有引力を発見したアイザック・ニュートンがロバート・フックに宛てた手紙に「巨人の肩の上」と言う言葉があります
ご存知ですか?
久保田:いえ、どういうことなんですか?
藤川:丁寧に引用すると「私がかなたを見渡せたのだとしたら、それは巨人の肩の上に乗っていたからです」という文章です
これは、先人の積み重ねた発見に基づくことで、より新しい発見することことができたということです
僕も学生さんと一緒になって多くを学んで、アイデアをどんどん出して、研究を発展させることができればいいと思っています
久保田:たしかに、科学の発展って地道な積み重ねですもんね、納得です
学生の皆さんへのエール
久保田:最後になりますが、藤川先生から私たち学生向けたにエールの言葉をいただきたいのですが
藤川:皆さんも、十分な準備の下に巡ってきたチャンスをいかに掴むかが重要だと考えていると思います
一方で、今日お話しした研究の経緯にも通じますが、偶然の機会いから新しい局面が開けることも多くありますので、僕はこのような偶然の出会いも大切にしたいと考えています
そこで、次の言葉を送ります
「アンテナを張れ!チャンスを見逃すな!偶然を楽しめ!」
久保田:私も先生の言葉を心に留めて研究に邁進したいと思います!
今日はお話をいただきましてありがとうございました

分子生命科学科 教員インタビュー 記事一覧は こちら









